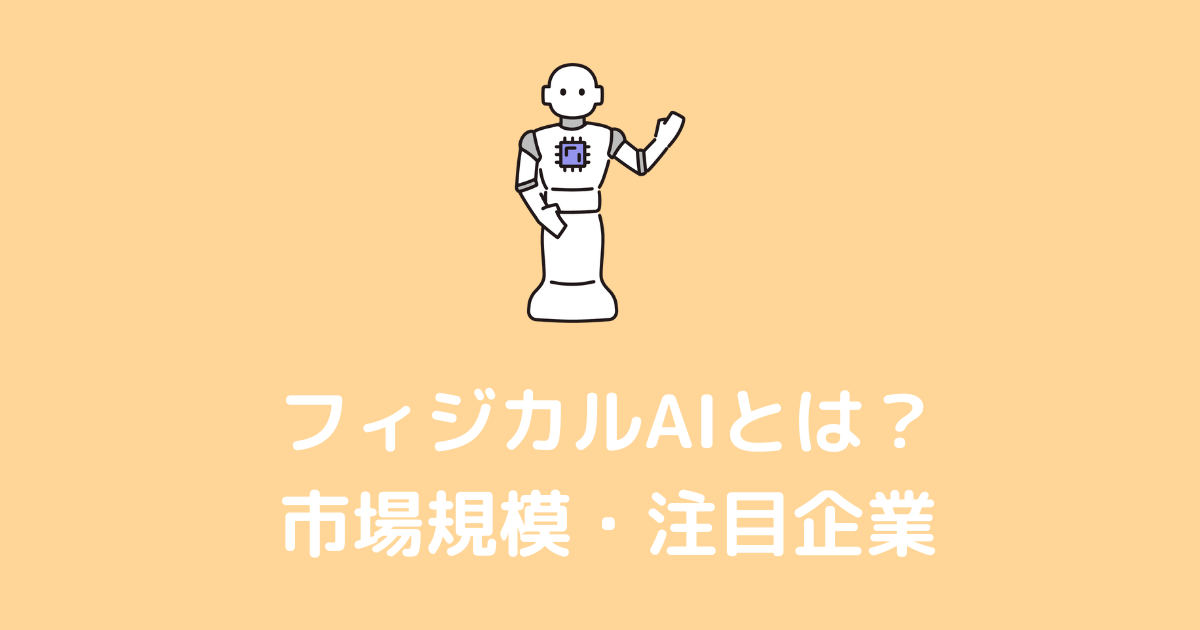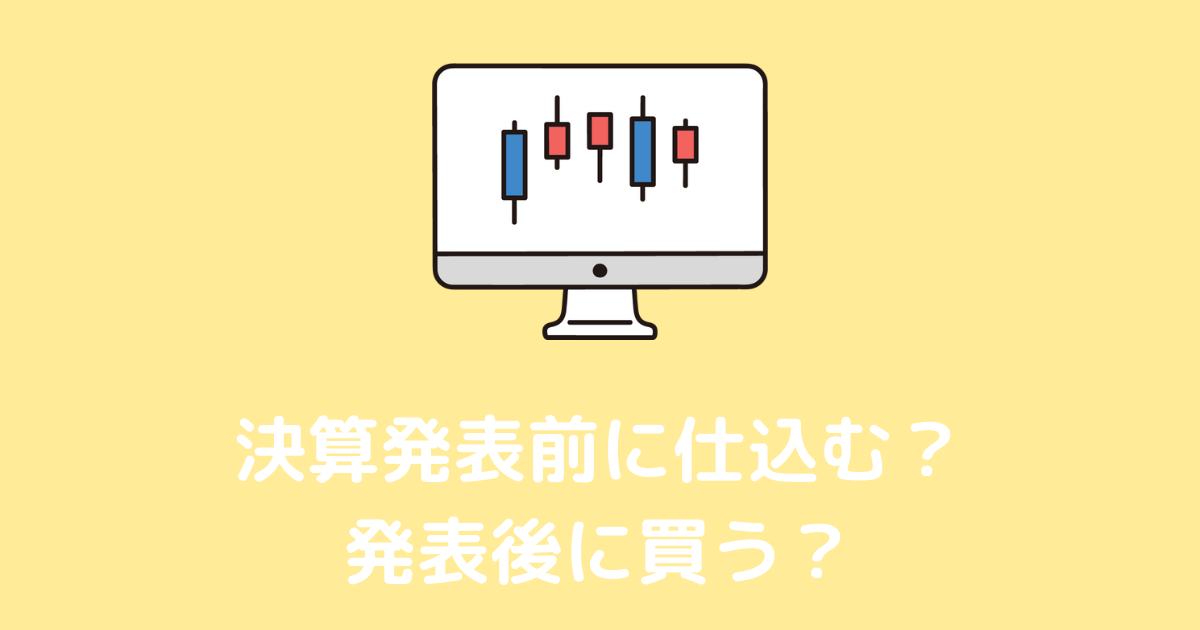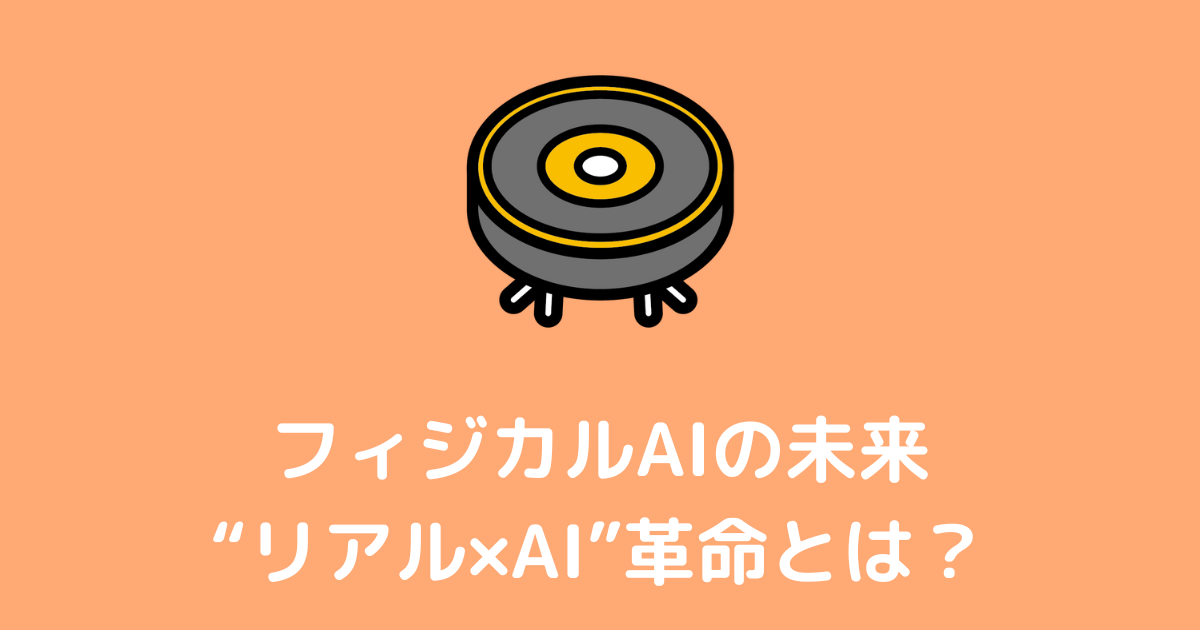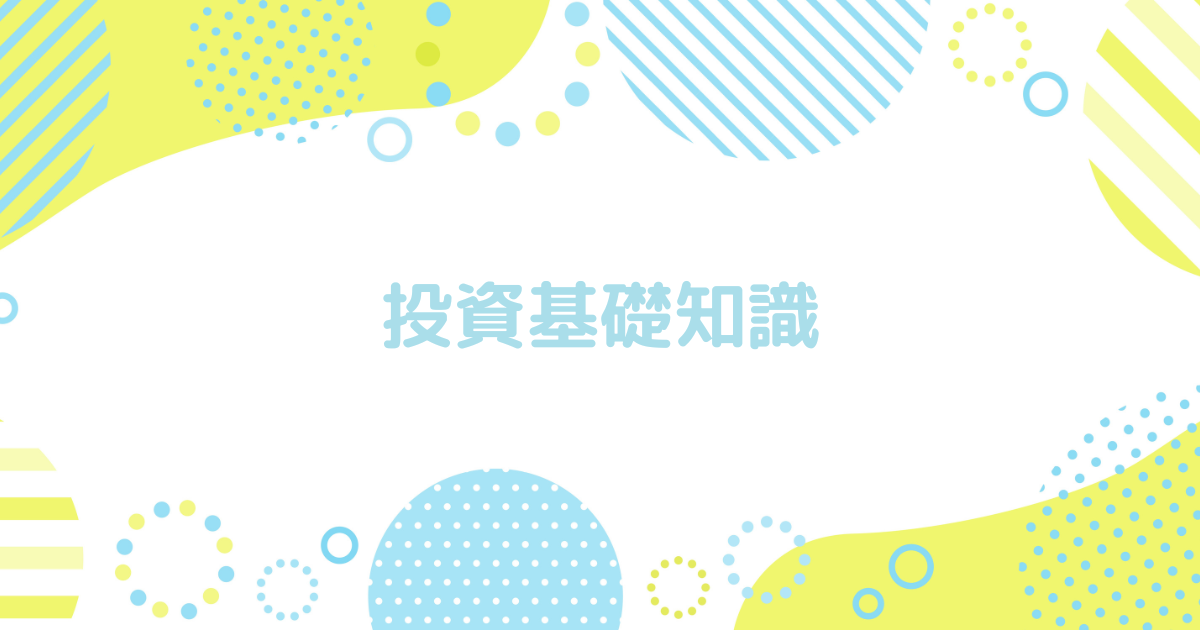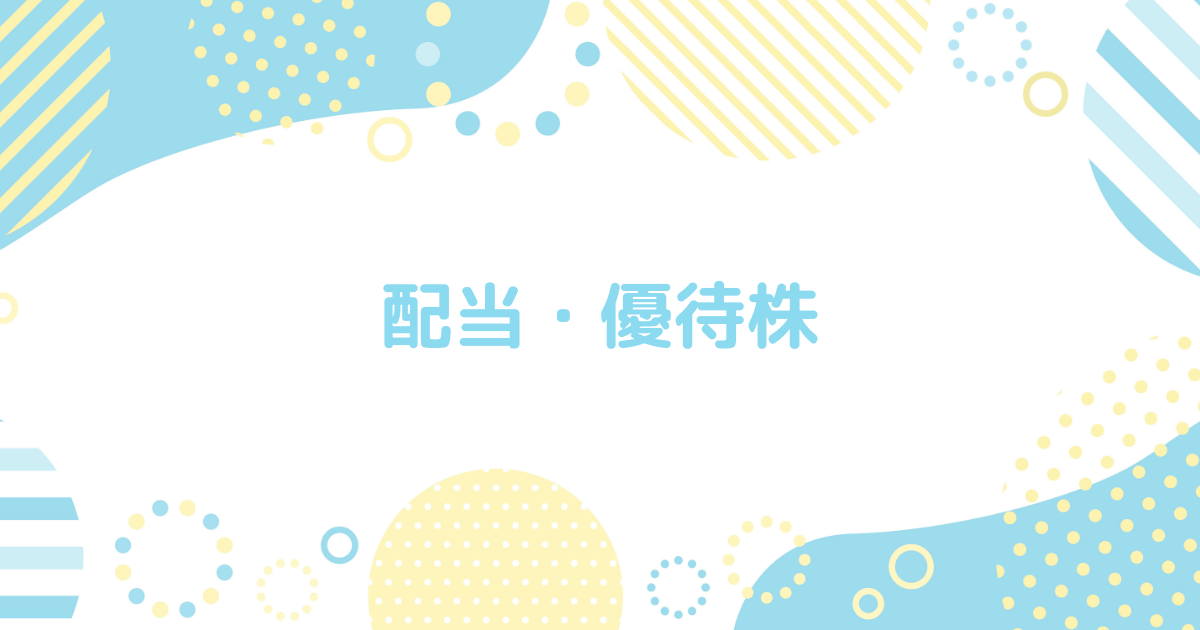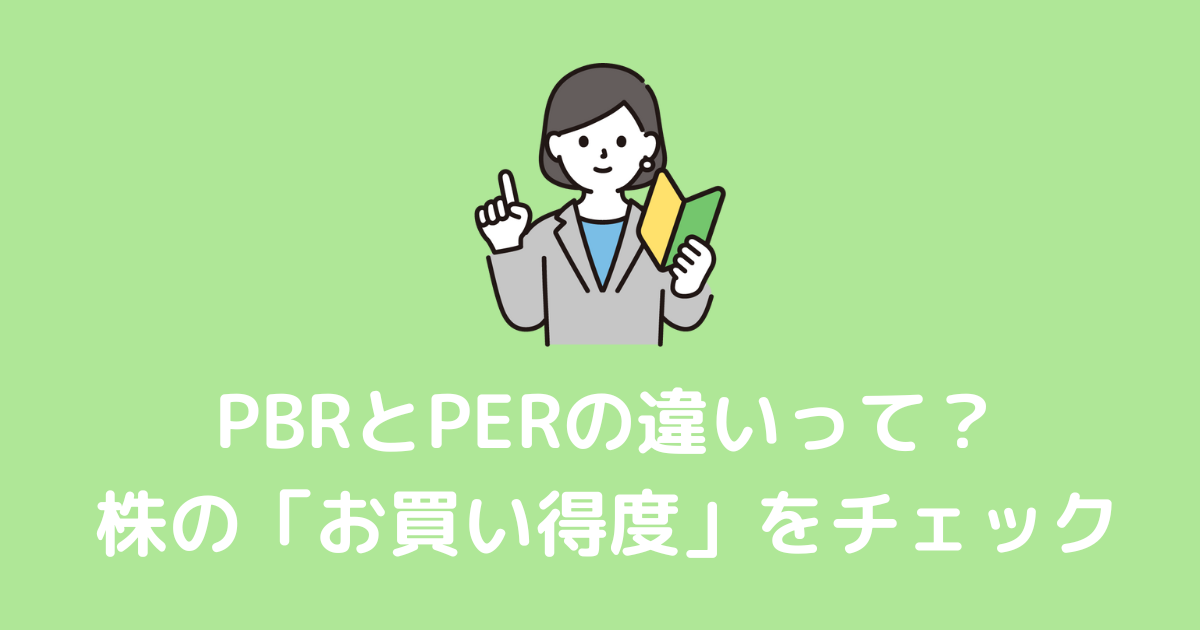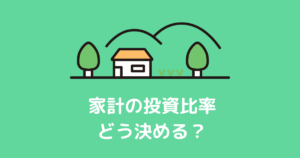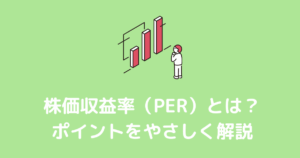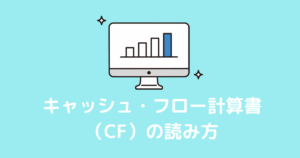教授、株の本を読んでたら「PBRが低いと割安」とか「PERが高いと割高」って書いてあったんですけど、正直ぜんぜんピンとこなくて…。



そうだね。投資を始めた人が必ずつまずくポイントだよ。言葉は似てるけど、見ている対象が全く違うんだ。



えっ、そうなんですか?なんだか兄弟みたいな言葉だから、てっきり同じ系統かと思ってました。



例えるなら、PBRは「家の資産価値と売値を比べる」ようなもの。PERは「家賃収入と値段を比べる」ようなものだよ。



なるほど!たしかに同じ“家”でも、見る視点で意味が変わるんですね。



そういうことだ。今日はまずPBRから順番に整理してみよう。
株のお買い得度を測る2大指標
株式投資をしていると必ず耳にする「PBR」と「PER」。どちらも株価が“お買い得”かどうかを測るための代表的な指標ですが、初心者にとっては混同しやすい概念です。
この記事では、まず PBR(株価純資産倍率) とは何かを丁寧に解説し、次に PER(株価収益率) との違いを整理していきます。投資初心者でも、「この株は資産に対して高いのか安いのか」「利益に対して買われすぎているのか」を理解できるようになるのがゴールです。
株式市場は日々値動きがありますが、冷静に数字を見ることで「割安株」や「割高株」を見分ける力がついていきます。数字だけを鵜呑みにするのではなく、どう活用するのかを理解することが大切です。



株って結局「高い・安い」って感覚で選んじゃうことが多いんですけど…。



だからこそPBRやPERといった“物差し”を持つことが大切なんだ。客観的に数字で判断できれば、感覚に左右されにくくなるよ。
PBRとは?株価純資産倍率の基本
PBR(Price Book-value Ratio:株価純資産倍率)は、株価が会社の純資産に対してどれくらいの水準にあるかを示す指標 です。計算式はシンプルで、
となります。
例えば、ある会社の株価が1,000円で、1株あたりの純資産(BPS)が1,500円だった場合、PBRは 0.67倍 です。
これは「会社を解散して資産をすべて株主に分配したら、理論上は株価より多くの資産が戻ってくる水準」という意味になります。
PBRが1倍を下回る意味
PBRが1倍以下というのは、株価が純資産を下回っている 状態を表します。一般的に「割安」とされる水準ですが、必ずしも投資妙味があるとは限りません。
- 割安の理由が「業績不振」である場合、投資家に見放されて低PBRになっているケースもあります。
- 一方で、堅実な企業で低PBRが続いている場合、長期投資のチャンスになることもあります。
日本株での事例
たとえば、2025年時点で 大手銀行株や自動車株 などはPBR1倍を割り込んでいる銘柄が多くあります。これは「資産は大きいけど、収益力や成長性への評価が低い」という市場の見方を反映しています。



教授、PBR1倍割れってなんかお得に見えるんですけど、本当にチャンスなんですか?



いい質問だ。確かに“お得”に見える。でも大事なのは「なぜ1倍を割れているのか」だよ。成長性が乏しいからか、業績が低迷しているからか、その理由を必ず確認しないといけない。



なるほど…安いから買い!って単純に考えちゃダメなんですね。
- PBRは株価と純資産を比較する指標
- 1倍以下は「株価が資産を下回る」状態
- 割安かどうかは業績や成長性とあわせて判断が必要
PERとは?株価収益率の基本
次に紹介するのが PER(Price Earnings Ratio:株価収益率) です。PERは「株価がその企業の利益水準に対して高いのか安いのか」を示す指標です。計算式は以下の通りです。
例えば、株価が1,000円で、1株当たり利益(EPS)が100円の場合、PERは 10倍 となります。これは「その企業が今の利益水準を続けるなら、株価を利益で回収するのに10年かかる」というイメージです。
PERが低い場合
PERが低い(例えば5倍以下)の場合、「株価が利益に対して割安」と解釈されます。ただし、業績不振や将来の利益減少が予想されるために低PERとなっているケースもあるため、必ず背景を確認する必要があります。
PERが高い場合
逆にPERが高い(例えば30倍以上)の場合は、「株価が利益に対して割高」とされます。ただしこれは必ずしも悪い意味ではありません。急成長が期待される企業や、新規事業への期待感が大きい場合は高PERでも投資家が買い続けることがあります。
日本株での事例
例えば、2025年時点で 任天堂 のPERはおよそ20倍前後。安定した収益とゲーム市場の拡大期待が背景にあります。一方、急成長が見込まれる新興IT企業ではPERが100倍を超えることも珍しくありません。



教授、PERが高いからダメっていうわけじゃないんですね。



そうだよ。PERは“将来の期待”も織り込むから、高いからこそ「この会社は成長株」と評価される場合もあるんだ。大切なのは、PERが高い理由を自分で考えることだね。
PBRとPERの違いを整理しよう
ここまででPBRとPERをそれぞれ理解しました。ではこの2つの指標はどう違うのでしょうか?
比較の視点
- PBR(資産を基準にする)
→ 株価が会社の純資産に対してどの水準にあるかを見る。
→ 主に「解散価値」や「資産の裏付け」に注目する投資家が使う。 - PER(利益を基準にする)
→ 株価が会社の利益に対してどの水準にあるかを見る。
→ 企業の「稼ぐ力」に対して株価が高いか安いかを測る。
つまり、PBRは資産の安全性を見る指標、PERは収益力を見る指標 だと言えます。
表で整理
| 指標 | 計算式 | 見ている対象 | 割安とされる目安 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| PBR | 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS) | 資産 | 1倍以下 | 成長性が低いと安くても魅力薄 |
| PER | 株価 ÷ 1株当たり利益(EPS) | 利益 | 10倍以下 | 赤字企業では算出不能 |



PBRは「どれだけ資産を持ってるか」、PERは「どれだけ稼いでいるか」を見るってことですね!



その理解でバッチリだよ。だから両方を組み合わせると「資産の裏付けがあって、利益もしっかり出ている割安株」を見つけやすくなるんだ。
投資での使い分け
- 長期投資家 → PBRを重視。資産をしっかり持っている企業は倒産リスクが低い。
- 成長株投資家 → PERを重視。利益成長に期待して株価が上昇する企業を探す。



じゃあ初心者はどっちを見ればいいんですか?



両方だね。PBRだけだと“安いけど伸びない株”をつかむかもしれないし、PERだけだと“人気先行の株”に飛びつく危険がある。だから2つをバランスよく見ることが大事なんだ。
- PERは「利益」に基づいた株価の割安度を測る指標
- PBRとPERは「資産」と「利益」という違う軸を見ている
- 両方を組み合わせて判断することで、より精度の高い投資判断が可能になる
実際の活用事例|割安株の見つけ方
投資の現場では、PBRとPERを組み合わせて「割安株」を探すのが一般的です。ここでは、実際にどう使われているのかを見ていきましょう。
1. PBR1倍割れの大型株を探す
PBRが1倍を下回っているということは、株価が純資産以下で評価されていることを意味します。特に銀行や不動産など資産を多く持つ業種では、1倍割れ銘柄が見つかることがあります。
例として、大手銀行株。日本のメガバンクは長らくPBRが1倍を割り込んでいました。しかし金融環境が改善すると、低PBRの銀行株が見直され、株価上昇につながったケースもあります。



教授、1倍割れって「お宝探し」みたいですね。



そうだね。ただし「割安放置株」という言葉もある。市場が評価しない理由がある場合も多いから、慎重に見極める必要があるよ。


2. PERが10倍以下の安定株
PERが10倍以下の企業は、利益に対して株価が低い水準にあると考えられます。特に成熟産業の企業で、安定的に利益を出し続けている銘柄は「堅実な投資先」として注目されやすいです。
例えば、自動車メーカー。トヨタやホンダといった大手は、利益を安定的に稼ぎながらもPERが10倍前後で推移することが多く、投資家から「割安に放置されている」と見られるケースもあります。
3. PBRとPERのダブルチェック
最も効果的なのは、PBRとPERを両方チェックする方法です。
- PBR1倍以下かつPER10倍以下 → 資産も利益も割安とされる「二重にお買い得」な株
- PBRが高くてもPERが低い → 利益に対して割安
- PERが高くてもPBRが低い → 資産に対して割安
こうした組み合わせを見ることで、より立体的に企業の評価を行うことができます。



つまり「両方クリアしてたら当たり株」って感じですか?



それはあくまで“入口”だね。本当に当たりかどうかは、業績の継続性や成長戦略を見ないと判断できないんだ
注意点と限界|数字だけでは判断できない
PBRとPERは便利な指標ですが、万能ではありません。数字に頼りすぎると誤った投資判断をしてしまうこともあります。
1. 赤字企業ではPERが算出できない
PERは利益をベースにするため、赤字企業では計算できません。つまり成長企業でも、一時的に赤字ならPERは参考にならないのです。
2. 業種ごとの平均値が異なる
業種によって「適正」とされる水準が異なります。
- 銀行や保険:PBR1倍割れが普通
- ITや新興企業:PER30倍以上でも投資家が評価
一律で「低いからお得」「高いから危険」とは言えないのです。
3. 成長性を織り込めない
PBRは資産を、PERは利益を基準としていますが、どちらも「将来の成長」を十分に反映できません。AIやバイオのように成長余地の大きい分野では、高PERでも買われ続けることがよくあります。
4. 補助指標が必要
PBRとPERだけでなく、ROE(自己資本利益率)や配当利回りと組み合わせることで、より精度の高い判断が可能です。特にROEは「資産をどれだけ効率的に稼ぐ力に変えているか」を示すため、PBRとの相性が良いです。



数字だけで「割安株発見!」って喜んでたら危ないんですね。



そうなんだ。投資家の世界では「安い株には理由がある」とよく言われる。だから数字を入口にしつつ、その裏にある企業の事情を調べるのが大切だよ。



なるほど…じゃあPBRとPERはあくまで“入り口のドア”みたいなものなんですね。



まさにその通り。ドアを開けた先の中身を調べないと、宝の山なのかガラクタ置き場なのかは分からない。
- PBRとPERを組み合わせることで、割安株を探しやすい
- ただし数字は万能ではなく、赤字企業や成長株には限界がある
- 業種ごとの水準や他の指標と組み合わせることが重要
まとめ|PBRとPERをどう活用するか
ここまで、株式投資の基本指標であるPBR(株価純資産倍率)とPER(株価収益率)について整理してきました。
両者はどちらも株の「お買い得度」を測るための道具ですが、見ている対象は異なります。
- PBRは資産を基準に評価する指標
→ 株価が純資産と比べて割安か割高かを判断する。1倍以下は「資産価値に対して安い」とされるが、成長性や収益力が伴わないと魅力が薄い。 - PERは利益を基準に評価する指標
→ 株価が利益に対して高いか安いかを判断する。10倍以下なら「利益に比べて安い」とされるが、業績悪化リスクが潜んでいる場合もある。 - 両者を組み合わせることで精度が増す
→ PBR1倍以下&PER10倍以下の銘柄は「二重に割安」として注目されやすい。ただし数字だけで判断するのは危険で、必ず業績や成長戦略を調べることが重要。
株式市場は常に変動しており、割安に見える株がいつまでも評価されないこともありますし、割高に見える株が長期間上がり続けることもあります。投資家に求められるのは「指標を正しく理解し、活用する姿勢」です。
投資家への実践アドバイス
- PBRやPERは“地図”のようなもの
道を歩くには便利だが、地形の起伏や天候までは教えてくれない。企業のニュースや成長戦略も合わせて調べること。 - 業種平均と比較する習慣を持つ
同じ数字でも、銀行業とIT企業では意味がまったく異なる。必ず業種ごとの基準値を確認する。 - 数字は入口、企業研究は本番
低PBRや低PERを見つけたら「なぜ割安なのか」を深掘りする。割安放置株なのか、単なる人気不足なのか、将来性の有無で評価は大きく変わる。



今日やっとPBRとPERの違いが分かってきました!でも正直、最初は「似たようなアルファベットだし混乱する」って思っちゃいました。



それは普通の感覚だよ。みんな最初は混乱する。でも一度理解すると「資産を見るPBR」と「利益を見るPER」ってシンプルに整理できるんだ。



でも数字を見て「割安!」って飛びつくのは危ないんですよね?



そう。安い株には安い理由があることが多い。市場が正しく評価していない場合もあるけど、成長性が乏しいから放置されているケースもある。そこを見極めるのが投資家の腕の見せどころだね。



なるほど…。じゃあ教授、もしPBRもPERも低い株を見つけたらどうしますか?



まずは決算短信を読んで、その会社の事業環境を調べるよ。例えば配当方針や海外展開、成長投資の内容をチェックする。それで「未来に伸びる」と思えば投資対象になるね。



うーん、投資って料理みたいですね。材料(数字)だけ見てもダメで、調理法(企業研究)次第でおいしくもマズくもなるって感じ。



いい例えだね。じゃあ君も「投資シェフ」として、数字をスパイスに研究を重ねていこうか。



はい!でもシェフとしてはまず、私の冷蔵庫の残高を増やす方が先かも…。



それも大事だね。投資の世界でも生活の台所でも、バランス感覚が一番大切なんだよ。
PBRとPERは株式投資の基本中の基本。数字を知るだけではなく、その裏にある企業の実態を読み解く力が必要です。数字をきっかけに「なぜ安いのか」「なぜ高いのか」を考えることで、投資判断の精度は確実に高まります。初心者はまずこの2つの指標を理解し、投資の第一歩として実践してみるとよいでしょう。