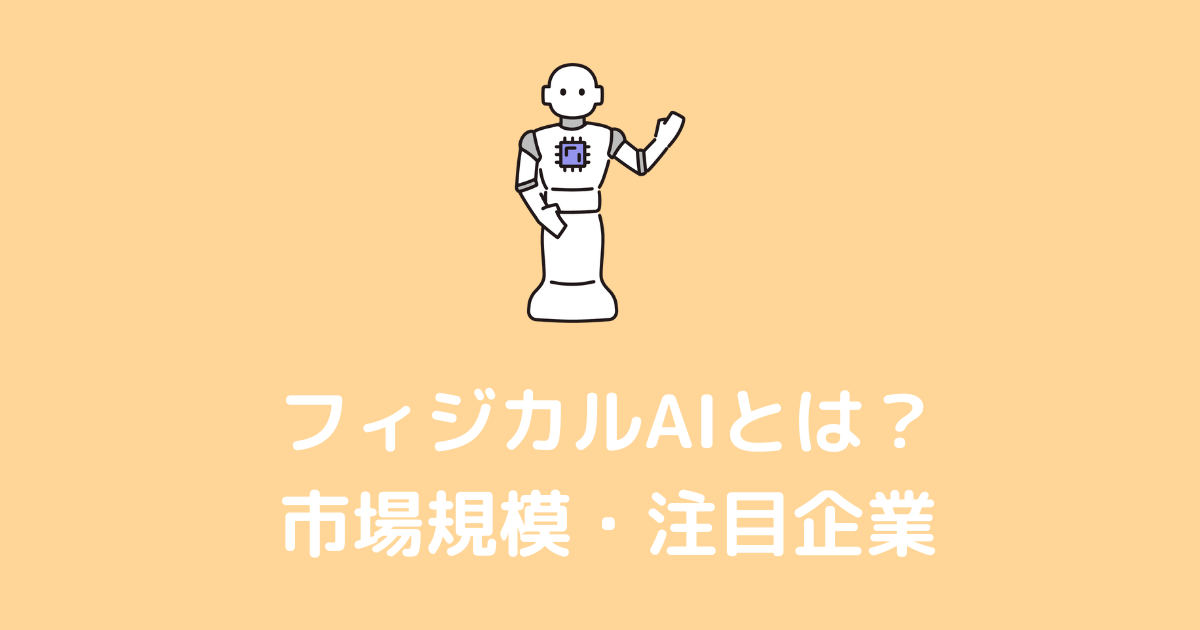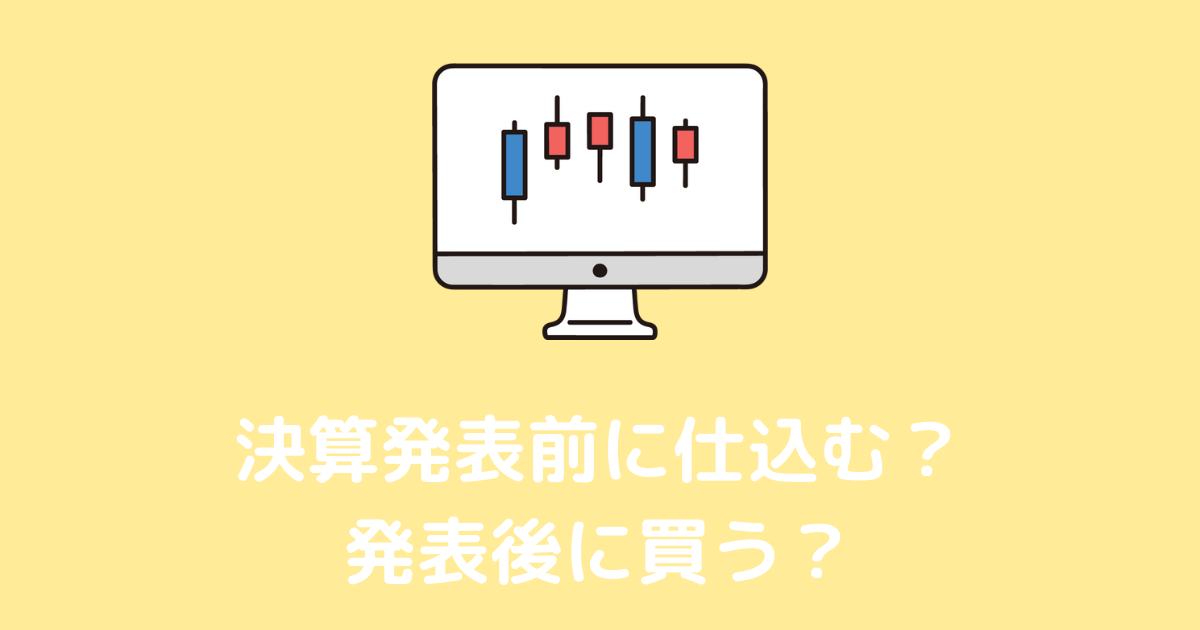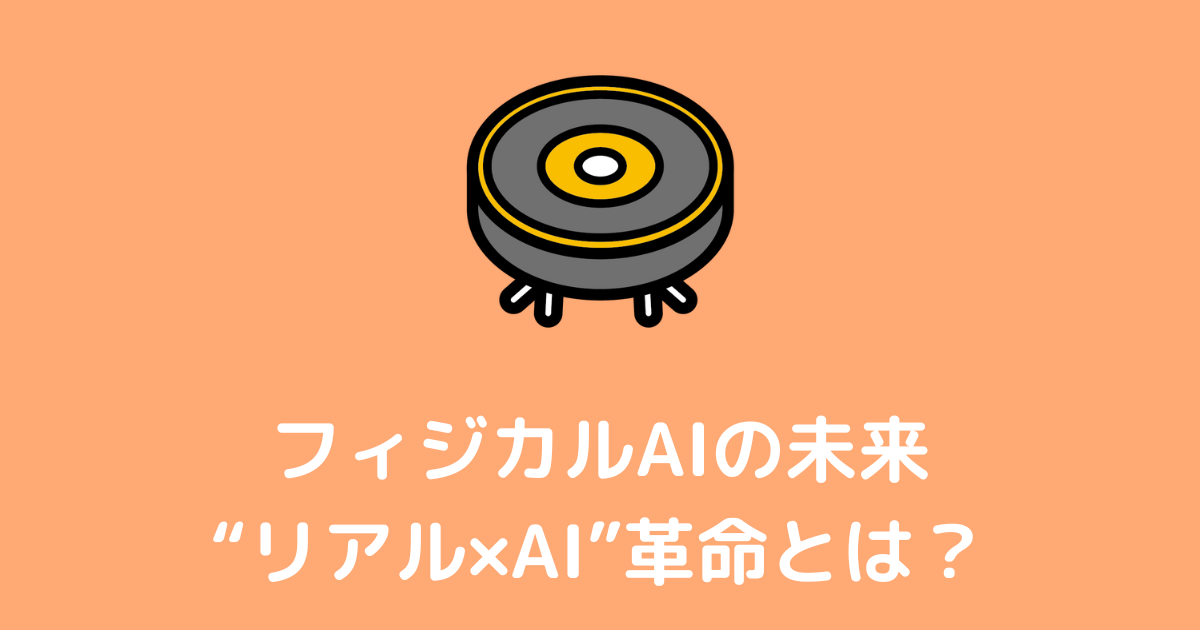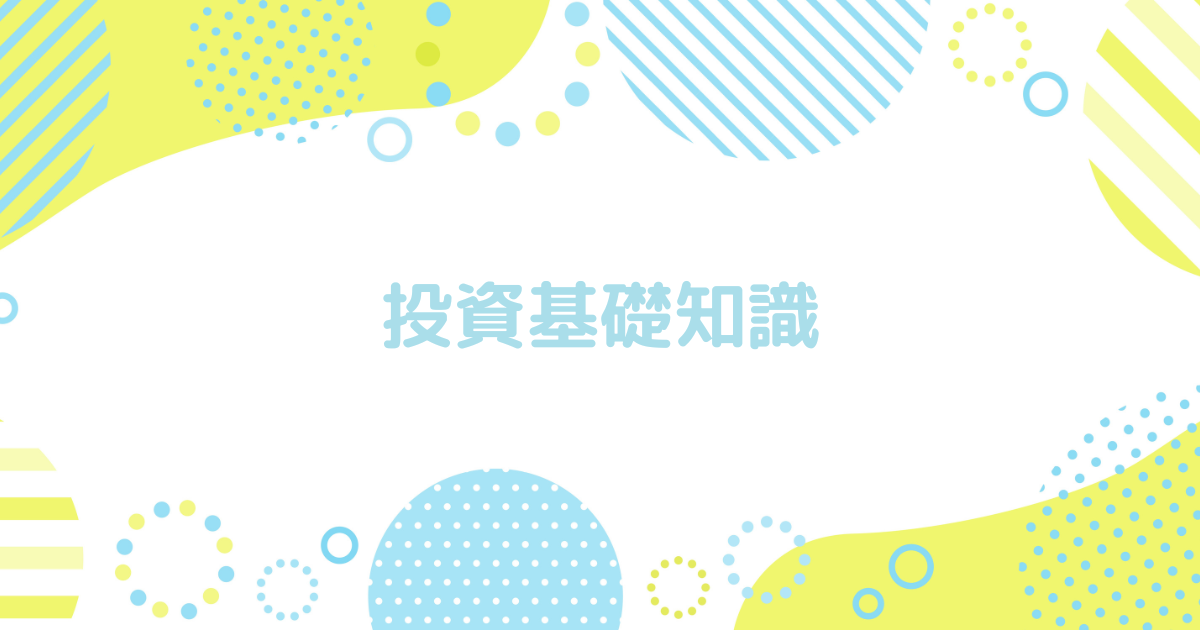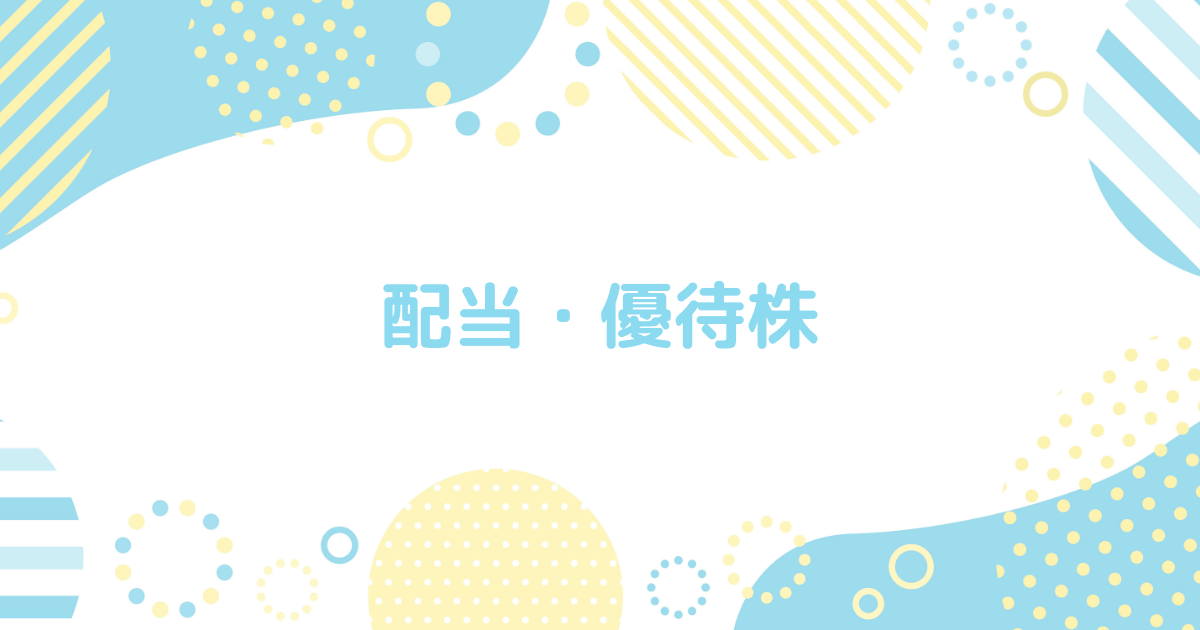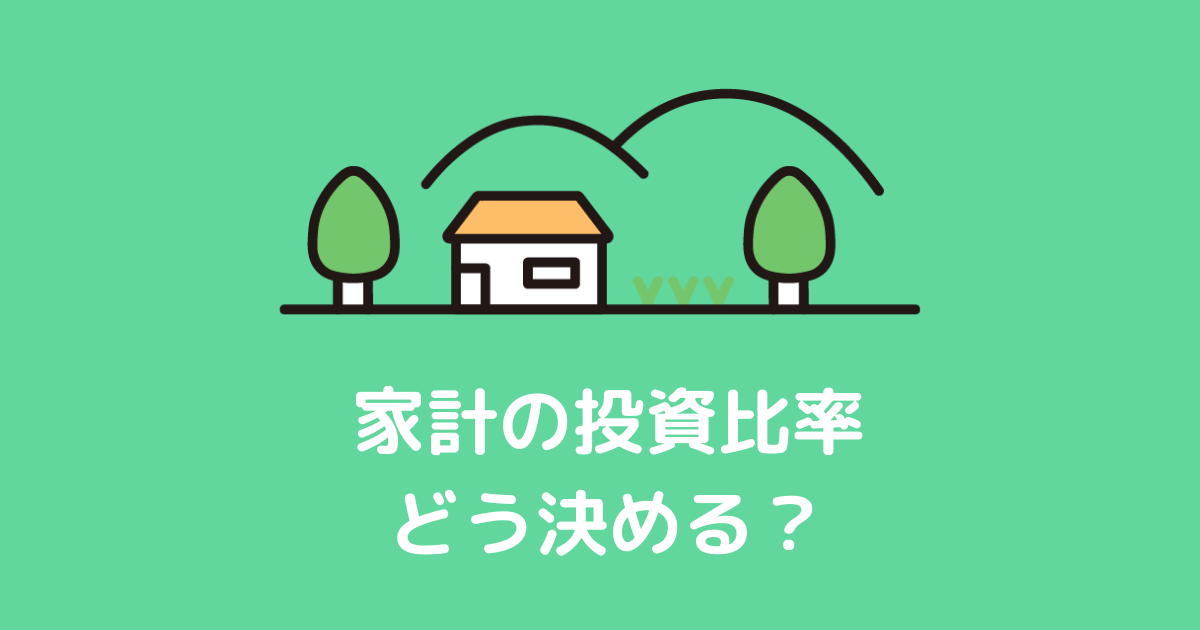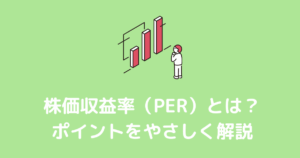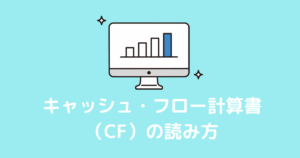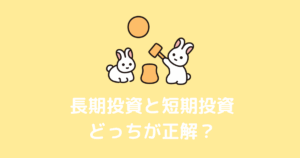「投資って毎月いくらが正解?」という永遠の悩み

最近、投資を始めたいという相談がどんどん増えてきてね。



やっぱり投資ブームなんですね。でも…みんな同じ悩みを抱えてません?



そう、「毎月いくら投資に回したらいいかわからない」だね。



そうなんですよ!
たとえば、友だちは「収入の3割を投資してる」とか言うし、
SNSでは「全額投資!」っていう猛者もいて…どれが正解なのか混乱します。



うん、その気持ちはよくわかるよ。
でも実は、“投資比率の正解”なんて存在しないんだ。



じゃあ…どうすれば!?



大事なのは“他人の比率をマネすること”じゃなくて、
自分の家計・性格・将来の計画に合った比率を見つけること。
そのための判断材料を、これからじっくり解説していくよ。



それ聞きたかったんです! 投資金額の迷子から卒業したいです。
投資比率を決める前に理解すべき3つの基礎(収入・支出・余力)
投資比率の話は、いきなり「手取りの◯%が理想!」というところから入る人が多いです。
しかし実際は、それだけで決めてしまうと危険です。
投資比率は、家計の「余力」によって決まります。
その余力を生み出す基礎は、次の3つです。
① 収入:手取りベースで計算する
まずは「年収」ではなく、手取り収入で考えることが絶対条件です。
年収500万円でも、手取りは380万円前後になるケースは珍しくありません。
ボーナスも確実に入るとは限らないため、あくまで日常生活に関わる“手取り”で判断します。
- 月の手取り:25万円
- ボーナス月の手取り:40万円
- 年間手取り:380万円ほど
ここが投資比率の「土台」です。
SNSを見ると「月10万円投資してます!」といった投稿も見かけますが、それが自分にとって可能とは限りません。
投資比率は、生活の余裕を削ってまで高めるものではありません。



投資は“背伸び競争”じゃないからね。



たしかに…。SNSの数字に気持ちが振り回されてました。
② 支出:固定費の最適化が比率のカギを握る
投資比率を決めるうえで、もっとも大事なのは「支出」、特に固定費をどれだけ抑えられているかです。
代表的な固定費は以下の通り。
- 家賃(住宅ローン)
- 通信費
- 光熱費
- 保険
- サブスク
- 車維持費
これらが高すぎると、投資比率を上げるのは難しくなります。
たとえば、
手取り25万円の人が固定費に18万円使っていたら、残せるお金は7万円しかありません。
逆に、固定費が13万円なら、12万円の余力が生まれます。
投資比率は“支出を減らす”ほど上げやすい。



なるほど…投資って「お金を増やす」だけじゃなくて「お金の流れを整理する」ことも大事なんですね。



そう。投資比率を上げるために必要なのは、まず“整理整頓”なんだよ。
③ 余力:生活を圧迫しない金額が最優先
投資比率は、この「余力」で決まります。
たとえば、
- 手取り25万円
- 固定費13万円
- 変動費8万円
→ 余力4万円
この余力4万円が、投資に回せる“上限”です。
もしここで「毎月5万円投資したい!」と掲げると、不足分の1万円をどこかで削る必要があります。
これが続けばストレスになり、投資をやめる原因にもなります。
“続けられる比率=正解の比率”
これが投資比率の本質です。



投資は短期勝負じゃないからね。



たしかに…ちょっと無理して続かないのが一番もったいない。
人生のフェーズによって比率は変わる
40代の場合、以下のような支出が増えがちです。
- 子どもの教育費
- 車の買い替え
- 住宅ローン
- 親の介護費の可能性
そのため、20代〜30代のような高い投資比率は現実的ではありません。
逆に50代になると、子どもの手が離れて投資比率を上げやすくなることもあります。
投資比率は「年齢・家族構成・仕事状況」で変わる。
だからこそ、ネットの誰かと比べても意味がありません。
“比率より継続”が優先される理由
一般的に言われる「収入の20%を投資に」という目安は、もちろん参考にはなります。
ただし、
- 無理なく続けられるか
- 心が苦しくならないか
- 家族との生活を犠牲にしないか
この3つをクリアしなければ意味がありません。
投資は、筋トレよりも“継続力”が資産に直結します。



比率は“目的地”じゃなくて“交通手段”みたいなもの。大切なのは走り続けることだよ。



すごく納得しました。これで比率迷子から抜け出せそうです!
- 投資比率の正解は「人によって違う」
- 収入・支出・余力の3つをまず把握する
- 無理なく続けられる比率こそ正しい比率
- 年齢・家族状況によって変えてOK
ステップ1|“守りの生活費”を先に確保する
投資比率を決めるとき、多くの人が最初に考えがちなのが「毎月どれくらい投資に回せるか?」という部分です。
しかし本当に最初に考えるべきなのは、“投資に回すお金”ではなく、“生活に必要なお金”です。



えっ、投資の話なのに“生活費”なんですか?



そう、むしろ投資の9割はここで決まると言ってもいいほど大事なんだ。
生活防衛費は「最低3〜6ヶ月分」を目安に
まず確保すべきは、万が一に備えた「生活防衛費」。
これは失業・病気・予期せぬ出費に備える“緊急用のお金”です。
一般的な目安はこちら。
- 独身:3ヶ月分の生活費
- 共働き:3〜4ヶ月分
- 子育て家庭:6ヶ月分以上
つまり、月20万円の支出であれば、最低でも 60〜120万円 を現金で確保しておくと安心です。
この生活防衛費がないまま投資を始めると、急な出費が発生した時に「投資資産を崩す」ことになり、長期投資のメリットがなくなってしまいます。



投資をする前に、“土台となる安心”を作っておく。これが成功の近道だね。



生活防衛費って、家の基礎作りみたいなものなんですね。
「固定費の見直し」で投資の余力が一気に増える
生活費の中でも、とくに重要なのが固定費。
固定費が1万円下がるだけで、年間12万円もの資金が投資に回せます。
代表的な固定費の見直しポイント
- スマホをキャリア→格安SIMへ
- 不要なサブスクの解約
- 生命保険の過剰な契約を整理
- 電力会社の乗り換え
- 車の維持費の見直し
例えば、
スマホ代8,000円 → 3,000円に下げられれば、年間6万円の投資余力が生まれます。



「投資に回せるお金がない!」という人ほど、固定費に穴があるケースが多いね。



わかります…。スマホとサブスクでかなり持っていかれてました。
家族持ちの投資比率は“余裕”がすべて
40代の家庭は、教育費・食費・住宅ローンなど支出が多く、20代・30代より投資比率を高くするのが難しいです。
しかし逆に言えば、ゆるく・少額でも続けることができれば、40代でも十分間に合うのが投資の良さです。
たとえ月1万円の積立でも、20年運用すると 約409万円(年利5%想定) まで増える可能性があります。



えっ、1万円でもこんなに…!



大事なのは“比率より継続”ということだね。
ステップ2|“安全圏の投資比率”を出す簡単計算式
生活費と余力が把握できたら、いよいよ投資比率を計算します。
ここで難しく考える必要はありません。
投資比率はこの式で決めればOK
投資比率(%)=(投資に回せる金額 ÷ 手取り収入)× 100
たとえば、
- 手取り25万円
- 投資に回せる余力が4万円
であれば、
→ 投資比率 =(4万円 ÷ 25万円)×100 ≒ 16%
この 16% が、その人にとって無理のない安全圏の投資比率です。



あれ、思ったより簡単ですね!



そう、必要なのは“背伸びしない数字”を出すことなんだ。
目安は「手取りの10〜20%」でOK
一般的な推奨比率は、手取りの10〜20%。
しかし無理して20%に近づける必要はありません。
逆に、この数字に満たなくても問題なし。
- 月1万円(月収の4%)
- 月2万円(月収の8%)
これくらいでも立派な「継続できる投資比率」になります。
大切なのは、
“続けられる比率を選ぶこと”
これだけです。
ボーナスの投資比率は“変動型”でOK
ボーナスをどう扱うか迷う人も多いですが、実はボーナスは“変動比率”で問題ありません。
- 生活費に使う期 → 投資比率を0%に
- 余裕のある期 → 50%を投資に
- 大型家電や旅行に使う期 → 投資比率を下げる
ボーナスは年ごとに必要な支出が変わるため、固定比率にすると逆にストレスになります。



つまり、ボーナスは「臨機応変」でいいんですね!



そう。投資比率も“柔軟さ”が大事なんだ。
ペース配分は“投資:貯金=7:3”を参考に
もし何から始めていいか迷ったら、まずは以下の比率がおすすめ。
- 投資70%(積立NISA・高配当株)
- 貯金30%(生活防衛費)
これをベースに、家計の変化に合わせて調整すればOK。
例えば、
子どもの進学で支出が増える時期は投資50%に下げたり、昇給して余裕が出たら投資85%に増やすなど。
“比率を変えていい”という柔軟性も、長続きの秘訣です。
家計モデル別|投資比率のリアルな例
投資比率の理想は家庭によって違います。
そこで、代表的な「3つの家計モデル別」に現実的で無理のない投資比率の例をご紹介します。
① 単身・1人暮らし(手取り23〜28万円)
最も自由度が高く、投資比率を上げやすい層です。
- 固定費が低ければ 15〜25%
- ゆる投資なら 10〜15%
- ボーナス月は投資比率を上げてもOK
例)手取り26万円・投資3万円 → 11.5%
② 夫婦+子ども1〜2人(手取り35〜45万円)
支出が増える時期なので、無理なく続けられる割合が重要。
- 教育費が多い → 5〜10%
- 住宅ローンあり → 5%前後
- A家計の平均例 → 手取り40万円・投資2万円 → 5%



やっぱり子育て世帯は投資比率を低めにしていいんですね。



そう。“継続できる比率”が最強なんだよ。
③ 共働き夫婦(手取り合計45〜60万円)
収入が安定しやすいため、投資余力も確保しやすい層。
- 積立NISA2人分 → 月6万円
- 追加で高配当株 → 月3万円
→ 合計9万円、投資比率 15〜20%
生活コストが低い場合は、投資比率を 25%程度 まで上げることも可能です。
やってはいけない投資比率の決め方|典型的失敗例
投資比率は「高ければ良い」というものではありません。
むしろ高すぎる比率は、挫折の原因になります。
失敗例1:SNSの投資比率を真似する
「毎月20万円積立!」という投稿は、あなたと生活環境が全く違う可能性があります。
SNSの比率は、あなたの正解ではありません。
失敗例2:生活費を削りすぎて投資比率を上げる
食費や教育費を削りすぎる投資は続きません。
投資の目的は“生活を豊かにすること”であり、生活を苦しめるようでは本末転倒です。
失敗例3:副業やボーナスに過度に依存する
ボーナスは不安定です。
過剰な期待で投資比率を上げてしまうと、急な減額時に資金繰りが崩壊します。
失敗例4:リスク許容度を無視して比率を決める
投資比率が高いほど、含み損に対するストレスも大きくなります。
心が落ち着かない比率は、長く続きません。
まとめ|投資は“比率”より“継続”。あなたに合う形が正解
投資比率をテーマにここまで見てきましたが、大切なのは「手取りの何%が正しいか?」という数字ではありません。
もっと重要なのは、あなたの生活を守りながら投資を長く続けられるかどうかです。



投資の必勝法は、結局“生き残ること”なんだよ。



うーん…深いですね。でもわかる気がします。
投資比率の“正解”は人によって違う
同じ30代でも、
同じ40代でも、
同じ年収でも、
人によって家計の状況や価値観はまったく違います。
- 子どもがいるか
- 車を持っているか
- 住宅ローンの有無
- 夫婦の収入バランス
- お金に対する不安の強さ
これらが異なる以上、「手取りの20%を投資しなきゃ!」という“画一的な正解”は存在しません。
投資比率は、
あなたの人生にフィットするようにオーダーメイドで決めるものです。
投資比率が低くても“積立の継続”が最強の武器
たとえ投資比率が5%でも、月1万円の積立が20年続けば 400万円以上 になる可能性があります。
10年続けば200万円以上。
「少ない金額でも積み上がる」
これこそが投資の本質であり、積立の強みです。
逆に、
月5万円投資しても1年で挫折してしまえば、長期積立には敵いません。



投資ってね、数字の強さより“継続力の強さ”のほうが大きいんだよ。



まさに筋トレと同じですね…。続かないと意味がない!
生活を守る余裕が“投資のメンタル”を支える
投資比率を決めるうえで最優先なのは メンタル です。
生活費に余裕があれば、株価が下がっても冷静に判断できます。
逆に生活ギリギリで投資している人ほど、含み損で動揺します。
- 家計に余裕がある
→ 投資のストレスが小さく、継続しやすい - 生活が苦しい
→ 投資比率が高いほどしんどくなる
だからこそ、投資比率を上げるための努力は“節約”ではなく“固定費の最適化”が重要なんです。
投資比率は一生同じでなくていい
人生は変化していくもの。
投資比率も柔軟に変えていいのです。
- 20代 → 投資比率高めでOK
- 子育て期 → 低めでOK
- 子ども独立後 → 再び比率アップ
- 50代 → 老後資金を意識して慎重に調整
大切なのは、その時々の“生活の現実”に合わせること。



比率って「固定」じゃなくて「調整」なんですね。



そう。投資比率は変えていいし、変えるべきなんだ。
“10年後に笑顔の自分”を目指すのがゆる投資の魅力
このブログのテーマにもあるように、投資は「頑張りすぎるもの」ではなく生活の延長線上にある習慣です。
- 積立NISAでコツコツ
- 高配当株で毎年のご褒美
- 優待株で生活を豊かに
この3つを自分のペースで組み合わせれば、10年後のあなたは今よりずっと“お金との距離が近い”はずです。



投資は“競争”じゃなくて“育成”だよ。



ポケモン育てるみたいな感じですね。



そうそう。急に強くならない。でも続ければ、確実に育つんだ。



じゃあ私、今日から“マイ資産”をコツコツ育てます!



うん。それがいちばんの投資成功法なんだ。